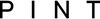PINTについて

「現代の民具」をテーマに活動しています。
民具とは、いろいろな定義があるかと思いますが、PINTでは、「自ら作り、自ら使う道具」と捉えています。
例えば、昔、農閑期に農家が稲藁でわらじを作るような。
売るためでも、見せるためでもなく、ただ自らが使うための道具。
美術品のような豪華さや輝きはなくても、静かに強く美しいもの。
そんなものに魅かれます。
ただ、今の時代においては、自ら作ることは現実的ではありません。
そこで、作るのは専門の作り手にお任せする。
ただ、考えるのは、作る人でも売る人でもなく、使い手自身。
現代の民具を作る上では最も近道な方法と考えていて、これを実現したのが「みんなのどうぐ」です。

ただ、この方法が適さないものもたくさんあるため、PINTが考えるものもあれば、作り手が考えるものもあります。オリジナルのものも、セレクトのものもあります。
伝えやすさや売りやすさなどの流通や販売に向けた部分は排除して、道具としての純度が高い、PINTなりの民具に近いものを紹介することを目指しています。
「道具」を考えるにあたって、大事に思っていること。
それは、日々たくさん、そして長く使えること。使い勝手と心地よく、経年と、触れて使う度に育ってゆくこと。
このためには天然素材が適しているので、使っています。こうした特性がなくならないように、メッキや塗装などのコーティングするような加工は行っていません。
その中でも、日本で長く使われ続けてきた素材、できるだけ今でも国内で作られた素材を扱っています。
長くこの土地で育ち、使われ続けてきた天然素材は、気候風土に最も適していて、機能的な特徴も活きると考えています。
使う度に育つのは、使う毎回が楽しい時間になり、これが実際は一番大事にしていることです。

製法は、伝統的な製法や、旧式の機械を使うことが多いです。
伝統自体への拘りではなく、現代の量産型を前提にした製法よりも時間も手間もコストもかかる場合が多いですが、出来上がるものの風合いが違ってくるためです。

PINTが紹介する道具をきっかけに、日々使い楽しむのはもちろん、素材やものを知ったり興味を持つきっかけになったら、とても嬉しいです。
そんな入口の扉を開く役割を担えたらと、素材や製法、作り手を少しずつ増やし、12年目になりました。
「民具」「道具」という言葉を使っていますが、同じように衣服も道具と捉え、同じ考えで並べて扱っています。
私自身も、作り手や使い手とのやり取り、自分も使い手の一人としてものと向き合うこと、興味の向くままに勉強を重ねながら、歩みを進めてゆきたいと思います。
これからも、PINTをよろしくお願いいたします。
2023.02 PINT 中地