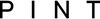(これまでの記事 企画概要・第1回目:素材を知る・第2回目:かたちを考える)
今回は、「かたちを作る」です。
長野県南木曽から、木地師の小椋さんに、ろくろの機械をお持ちいただきました。
実際に小椋さんに器を製作していただきながら、皆でその場で触り、かたちを考えます。
実際にデザイナーやバイヤーがするように(こんなに大人数なことはないと思いますが)、みんなで修正指示をかけ、最終サンプルを決定するのです。
商品の仕様を決定する大事な日です。
写真だと分かりにくいですが、3パターン、それぞれ微妙に違います。左から、
1:外側の縁が上がる幅20mm、浅めのS字
2:外側の縁が上がる幅20mm、深めのS字
3:外側の縁が上がる幅25mm、深めのS字
持ちやすさと見た目のバランスをみんなで検討して、
3:外側の縁が上がる幅25mm、深めのS字
に決定!
いつも感じることですが、図面だけでは判断ができないことなので、実際に職人さんと一緒に場所と時間を共にして作ることは一番大事です。
持ち上げやすく、食卓に置くときに置きやすく、指が縁の下にすっと入る形状に。置いたときの佇まいも美しく仕上がりました。
小椋さんも、このライブ感を楽しんで製作くださいました。
暮らし手自身による、しかも10名という大人数による企画制作。
じっくり時間をかけて、みんなが「我が子」のように考え話し合ってきた思いや、暮らし手の目線がぎゅっと詰まって、みんなのどうぐならではの素晴らしい製品になりました。
参加者の皆さんと、前向きにご協力下さり(今回で2回目)、僕たちのイメージと希望を高い技術と対話力で形にしてくださる職人の小椋さんあっての製作手法。
参加者の皆さん、小椋さん、お疲れさまでした。素晴らしい企画と製作、ありがとうございました!
こちらの製品の、先行受注予約を受け付けております。
先行予約のみ2割引ですので、是非ご検討下さい。
朝食の時間を愉しむ木のプレート(みんなのどうぐ1) 栃の木 8寸(24cm)
これから、今回で決定したプレートを最終サンプルとして、小椋さんに製作していただきます。
次回の最終回は、11月22日を予定しています。
完成品のプレートのお披露目&納品会を終えた後、みんなで一緒にこのプレートで朝ご飯をいただきます。
当初、朝ご飯を持寄りの予定でしたが、今回の製作中にとても盛り上がり、思いがけなかったスペシャルな企画が実現することになりました。
その内容は、次回のレポートで報告いたします。
撮影&進行アシスタント:NORIYUKI FUCHIGAMI
ありがとうございました!
中地