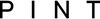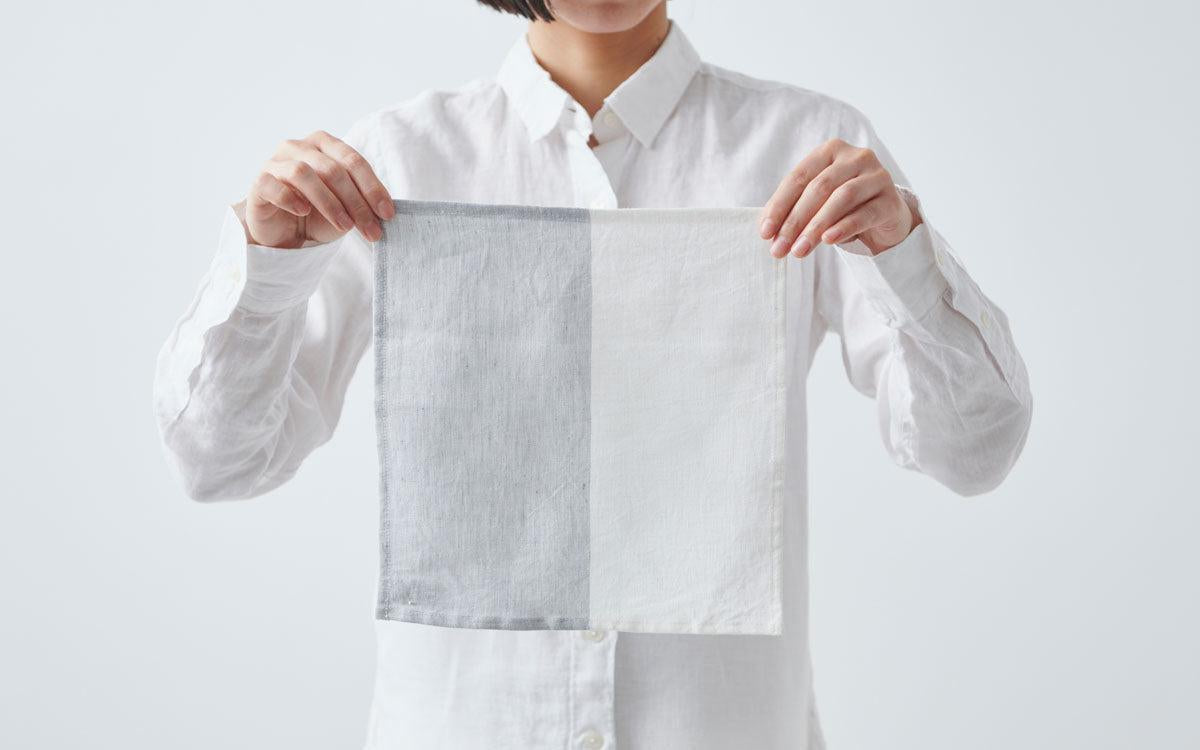赤畠大徳販売会2025 初日12/19 予約抽選制・販売方法のご案内
一つ前の記事で、販売会の概要を記載しています。合わせてご覧ください。 初日12/19 (金) に限り、各回45分の時間帯と人数枠を設け、赤畠さん作品のご購入権について事前抽選予約制となります。希望回を連絡お申し込みいただき、抽選を行います。 ▼事前抽選予約制の目的じっくり選んでいただくこと、お並び順に公平に安心して検討できること、包丁ですので狭い店内で安全を第一にということで採用した前回までの方法でしたが、寒い中長時間お待たせしてしまいました。そのため、最初の3点は保ちつつ並び時間を無くすため、今回は、初日12/19のみ事前抽選による予約制とします。 ▼時間帯12/19 (金) 12:00-12:4513:00-13:4514:00-14:4515:00-15:4516:00-16:4517:00-17:4518:00-18:45*通常とは営業時間が異なり、12-19時営業となります。 ▼ご予約方法 ・当店のインスタグラムのDM・お問い合わせフォーム より、「お名前」「電話番号」「第1〜第3希望時間帯」をお知らせください。当選された場合、ご入店時にお名前の分かる証明書のご提示をお願いしております。(本件以外の目的で使用、連絡することはございません) ご予約は、12/15(月)19:00まで受付いたします。 人数枠をご応募数が上回った場合、各回ごと、ご希望順ごとに抽選を行います。抽選結果が出ましたら、12/17(水)までにお知らせいたします。抽選結果は、当選有無に関わらずご連絡いたします。 ▼当日の販売方法当選の方に、別途詳細をご案内いたします。入店時、本人確認のため、必ずご本人とお名前の分かる証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポート等)をお持ちくださいますようお願いいたします。お持ちでない場合は恐れ入りますが当選は無効となり販売ができませんので、ご注意ください。 同時間帯のお客様には、皆様同時にご入店いただきますが、その中で急ぎ合いにならないよう、ご入店受付時に購入順をくじ引きで決める予定です。(方法は状況に応じて適宜変更する可能性があります) 購入制限:お一人様あたり 包丁2点・カトラリー2点 まで ✳︎在庫には限りがありますので、完売次第終了となります。✳︎当選は、ご希望品の購入を約束するものではありません。✳︎予約時間にご不在(連絡無し)の場合は無効となります。✳︎店内での撮影、スマートフォン、携帯電話の使用禁止とさせていただきます。当日は当選外の方も同様です。 当日、きりん屋のパン、常設品の販売は行っており、狭い店内のため場所を分けることはできないため、当選外のお客様もご入店いただけます。当選の方には、当日、各時間帯の開始時にご入店いただく際に、赤畠さんの注文表をお渡しいたします。 作品数に限りがありますため、ご不便おかけする部分もあることは承知の上ですが、できるだけ気持ちよく作品選びを楽しんでいただけたらと願い、今回の方法を採っております。 ご了承の上、ご応募いただけますようお願いいたします。