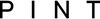藍染め 〜その5.植物の神秘、配糖体について〜
連載並みの藍染めレポートが続きます。 なぜ5000年以上も前のミイラを覆う布に藍染が使われていたりなど、日本だけでなく世界各国で藍染が使われていたのか不思議になりませんか? 藍色発見の一つの推測を職人さんが惜しみなく教えてくださいました。 まず人間と植物の大きな違いがあります。 植物は光合成と水と二酸化炭素でエネルギー源であるグルコース(ブドウ糖)を自分で作る事ができます。 我々人間は自分でエネルギー源であるグルコースをつくる事ができないため、植物など食べ物から摂取します。ですから我々は自分の足で歩きエネルギー源を捕獲するために動けるのです。 植物は動かなくても自給自足ができますのでご覧のとおり凛として地に入り動かないのです。 これって当たり前の光景だけどよくよく考えるとすごい事ですよね。フムフム 植物はブドウ糖を自給自足できます。ですが必要な時にブドウ糖を使うために色々な物質(A,B,C・・・)とグルコース(Glc)と結合で存在しています。 それが配糖体(A-Glc,B-Glc,C-Glc・・・)と言われるものです。糖が物質に配位しているから配糖体です。 藍染はインディゴという物質が青色を呈します。植物の葉っぱの中にインディゴとグルコースが結合した配糖体インジカンという状態で存在します。 糖が必要な時になると植物の中にある結合を切る酵素が働きます。インジカンを酵素によって切断をすると青色呈するインディゴとグルコースに分解されます。 普段は使う事がないため、酵素が働いていないので配糖体で貯蔵されています。 植物の葉っぱが緑なのはクロロフィルという葉緑素の色が緑だからです。 ですが、葉っぱを切ったり、枝を切断しますと植物が死にます。 そうすると結合をきる酵素の制御が切れて一気に切断の反応が進みます。 そうするとインジカンがたくさん含まれている葉っぱはインジゴがたくさん出てきて青色がでてくるってわけです。 結果、昔の人々は枯葉などを見た時に青色になっている植物に興味をもち、染色をしたらとても綺麗な色になったのでこの植物は藍染が出来ると断定していたのではないかという推測です。 多く含まれている植物としてタデ科の蓼藍、キツネノマゴ科の琉球藍、マメ科のインド藍、アブラナ科ウォードなどが挙げられます。 ただ単に高濃度インジカンがある植物が世界各国にあって偶然枯れ葉など見て昔の人が手を加えて藍染をしていた歴史。すんばらしい。 なんか化学からアプローチして歴史を紐解くと違った見方が出来て面白くありませんか? 余談ですが、私コジマは薬剤師をやっております。漢方薬のお話を少しさせて頂きます。 実は漢方薬も配糖体なんです。薬の効能があるものと糖が結合しているんです。 じゃあ何処で分解されているの?腸ーでーしょー(某予備校教師風) 人間の腸内細菌はたくさんの種類がいます。飲み始めて分解する腸内細菌を増やして分解をして有効成分が腸内から吸収し、生理活性を示すのです。 ですから漢方薬は効き目がでるのに時間がかかるのはこの腸内細菌の分解速度が関係しているからです。 あと飲んだり飲まなかったりする人(コンプライアンス不良)の人は、効き目が悪いのは腸内細菌が増えないからです。 まさか漢方薬の配糖体と藍染の配糖体がこんな形で繋がるとは思ってもいなかったのでびっくりです。 まだまだ知らない事だらけですが、違ったアプローチをどんどんして皆様に興味を持って頂けるように伝えられたら本望です。 坂由香里さんに本藍で染めていただいた絞り柄ハンカチ、限定個数で販売開始しました。...